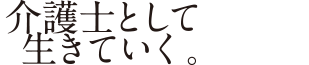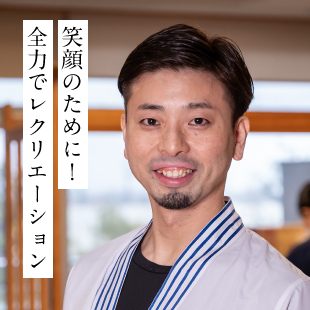見慣れたふるさとの光景は一瞬にして姿を変えた。2024年1月1日午後4時10分ごろ、最大震度7の揺れが能登半島を襲い、多くの建物が倒壊し、沿岸部では津波が発生。石川県内の介護福祉施設も深刻な被害を受けた。特別養護老人ホーム「長寿園」(珠洲市宝立町)に勤める3人のスタッフに、未曾有の大地震を振り返ってもらった。
馬渡 珠代さん 介護士長
久保田 良枝さん 主任管理栄養士
善野 由美子さん 看護師
電気も水もない中で
近隣住民も受け入れ
―― 能登半島地震で、長寿園では停電や断水に加え、地盤沈下によるひび割れや亀裂が発生するなど、大きな被害を受けました。馬渡さんと久保田さんは地震発生時、長寿園で働かれていたそうですね。
馬渡● はい。立っていられない強い揺れで、正月気分は一気に吹き飛びました。いたるところで土砂崩れが起き、交通網もずたずた。隣接する能登町の自宅に戻るには、大渋滞の中を何カ所も迂回していく必要がありました。給油できるかどうかも分からず、結果的にその日から6日間ほど長寿園に寝泊まりしながら入所する皆さんのケアにあたりました。
久保田● 馬渡さんと同じく、私も自宅に戻れない日が続きました。地震発生後は広範囲で携帯電話がつながりにくく、施設の非常用電話に家族から連絡があったのですが、会話はほとんどできず・・・。不安はありましたが、ケガもなく避難していることは分かりましたので、その後は施設の仕事に専念しました。
善野● 私は当日お休みで、津波への警戒を呼びかける放送が続く中、高台に上がるなどしてその日は家族で寄り添って不安な夜を過ごしました。2日は出勤でしたから遠回りしながらも何とか長寿園近くまで来たのですが、周辺の道路が通行できず、その日はやむなく帰宅。翌日は主人に送ってもらい、どうにか長寿園にたどり着きました。同僚や入所者の方々の顔を見たとき、ぽろりとほおをつたうものがありました。
―― 長寿園は高台にあり、入所者やデイサービスの利用者だけでなく、地震直後は地域住民の皆さんも避難されていました。
久保田● 施設で非常用にストックしていたのは入所者用の食料や水だけ。しかも、3日分しかありませんでした。能登へのアクセスが遮断され陸の孤島となる中、なかなか支援の手も届きません。備蓄米でおにぎりを作って提供しましたが、十分な量を確保することはできず、心苦しい思いもありました。
―― 停電や断水が続く中、入所者の方に対してはどのようにケアをされたのですか。
馬渡● 水が使えないので、入浴や洗濯などができません。ですから、オムツ交換などは必要最低限に抑え、ごみ袋を使ったポータブルトイレを設置しました。停電中はナースコールや転落防止用のベッドのセンサーも機能しないので、サポートが必要な方には食堂や廊下など職員の目が届く範囲に集まっていただきました。ほとんど眠ることはできませんでしたが、自分の体調を気にする余裕はなく、目の前のことに必死でした。
久保田●「食」に関しても通常時とは全く異なります。ミキサーが使えず、介護職のスタッフにも手伝ってもらい、おかゆ状のものを手作業でつぶしながらミキサー食の代わりにしたり、ストーブの熱だけでカレーを調理したりと工夫しながら対応しました。それでもやはり、生鮮食品が手に入らず、エネルギーや栄養の不足はとても気になりました。
善野● 衛生環境は悪く、栄養も十分に取れず、嘱託医の先生も来ることができません。このような状況で、看護師として一番気になったのは、「感染症」です。何人かインフルエンザや新型コロナにかかる人はいたものの、早期に隔離するなどの対応で何とかまん延を防ぐことができました。数日たって災害派遣医療チーム(DMAT)の方が駆けつけてくれたときには、心からほっとしたことを覚えています。

全国のサポートを受けながら
徐々に落ち着きを取り戻す
―― 皆さん懸命に奔走されていたのですね。
馬渡● 3日目くらいからは1日の業務の流れがつかめ、6日目からは地域住民の皆さんも近隣の避難所へと移り始めました。そのころからですね。私たちスタッフも、少しずつですが、ひと息つく時間ができました。そして、1月中旬からは入所者の2次避難がスタートし、加賀方面や県外の介護福祉施設へと9割近い方が移っていきました。
善野● ほっとしました。感染症の広がりで、体力の落ちた入所者を危険にさらすことが最大の心配事でしたので。「これで安心して生活してもらえる」と思いました。
久保田● 並行して、さみしい気持ちがあったのも事実です。「元気に戻ってきてくれるだろうか」「このまま長寿園がなくなってしまうのではないか」という不安もありました。もちろん、職員の中にも住む家を失ったり、避難したりしている人が多く、地震が引き金となって離職するスタッフも少なくありませんでした。
―― そんな中、長寿園を運営する社会福祉法人長寿会では、1月下旬にはデイサービスを再開し、給水タンクを活用して入浴サービスも始めています。少しずつですが、長寿園でも以前の状態に戻っていますか。
馬渡● いまだに施設内には段差が残っていますし、水が使えない部屋もあります。それでも、3月中旬からは避難されていた入所者も随時戻ってきています。「おかえりなさい」と皆さんを再び迎えられるのが、本当にうれしかったです。
久保田● 全国から寄せられる善意も、とても心強かったですね。生鮮食品を届けてくれたり、焚き出しで温かい食べ物を振る舞ってくれたりしてくれました。
善野● 一時、私も含めて看護師2人で入所者の健康管理を担っていた時期がありました。その時、DMATで来られた医療従事者の方々が長寿園も気にかけてくれて、市内の避難所を回った後に立ち寄ってくれることもよくありました。
馬渡● 全国老人福祉施設協議会等を通して、長寿園に来てくれた介護士の応援職員もたくさんいらっしゃいました。関東や九州など、全国各地から駆けつけてくれた同業者の皆さんが、人手不足に悩む私たちにとって大きな支えとなりました。ほかにも、能登には自衛隊や警察関係者、ボランティアの方など、本当に多くの支援をいただいています。人の温かさをこれほど感じたことはなく、長寿園のスタッフとしても、能登で生きる一人としても、心から感謝しています。
地震を経た今だからこそ
災害への備えをより強く
―― 能登半島地震からこれまでの歩みは、初めてづくしだったと思います。この経験を通して得たものはありますか。
善野● 間違いなく、「団結力」は高まりましたね。昼も夜も、これほどスタッフのみんなと同じ時間を共有したことはありません。職種に関係なく助け合い、「どうすればいいか」を何度も話し合いました。長年、顔を合わせていた同僚の今まで知らなかった一面に気づくこともありました。
久保田● 対応力も高まったかもしれません。調理部門でいえば、電気を使わず、節水しながらでも、少しでもおいしい食事を楽しんでもらいたいと工夫しました。住民の方からタマゴをいただいたときは、手作りのプリンも作りました。同時に、反省点もあります。ローリングストックをうまく活用しながらミキサー食などの在庫をもっと確保するなど、災害への備えをより充実させておけばよかったと感じています。
馬渡● 介護の観点でみると、停電や断水の中でトイレが一番の問題でした。凝固剤など、トイレ関係の備えを心がけたいですね。加えて、今回の地震は冬場に発生しましたが、夏だった場合、衛生面に対する問題はより深刻だったと思います。季節に応じた準備も考えておきたいテーマです。
善野● 確かにその通りですね。万一の際は、マニュアル通りにいかないことも多いかもしれません。ただし、「いざ」というときにスタッフが同じ方向を向けるように、心構えをしておくことはとても重要だと思います。

―― 今回の経験を糧に、災害に強い施設づくりを進めていくことは、能登だけでなく、地震大国である日本全体の課題と言えます。最後にうかがいます。復旧・復興へと歩みを進める皆さんは、長寿園をどんな施設にしていきたいと考えていますか。
久保田●「食」は大きな楽しみです。食材を配達してくれていた業者が廃業を決め、スーパーに調理員が買い出しに行くなど、まだまだこれまで通りとはいきません。ですが、工夫を凝らした行事食を用意するなど、入所する皆さんが「おいしい」と笑顔を見せてくれる食事を提供していきたいと考えています。
善野● 地震で職員数が減ったこともありますが、人手不足は能登だけでなく、介護福祉業界全体の課題です。看護師の立場でいえば、介護福祉施設では、病院で働く場合以上に医療的な判断が求められる場面が多く、同じ職種でも異なる働き方が必要です。その分、大変さはあります。半面、介護福祉施設で働くからこその魅力もたくさんあります。若い人たちにもっと介護士の仕事に興味を持ってほしいですね。私が働く長寿園には、素敵な仲間が多く、とてもアットホームな施設です。新しく入ってくる人材とともに、より温もりあふれる場所を築いていきたいと思います。
馬渡● 私も介護福祉の魅力を若い世代に発信していきたいです。長寿園には、人生の先輩方が入所されています。そんな皆さんの生活に少しでも笑顔を増やしたいと思っています。さらに言えば、入所者一人ひとりが歩んできた最期を、よくするのも悪くするのも、介護士が深く関係しています。人生に関わる責任感は極めて重い。ただ、その分、誇りもあり、やりがいもある職種です。介護士として輝く未来に、ぜひ多くの人が興味を持ってほしいですね。
生き方も、働き方も自由です
MY STORY